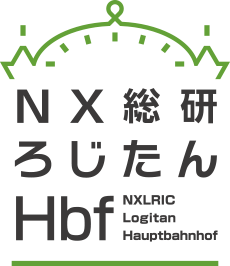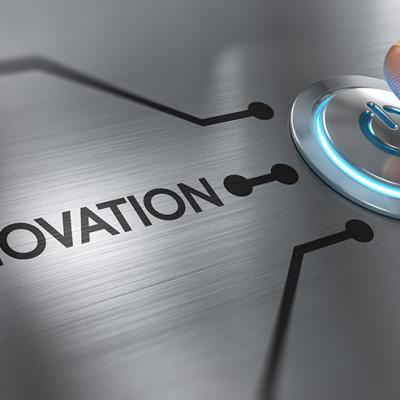2024年4月、NX総合研究所は「令和版 物流ガイドブック(概論編、フィジカル編、デジタル編)」を電子書籍Kindleにて出版しました。本書の出版に至った背景に触れつつ、簡単に本書の内容をご紹介したいと思います。
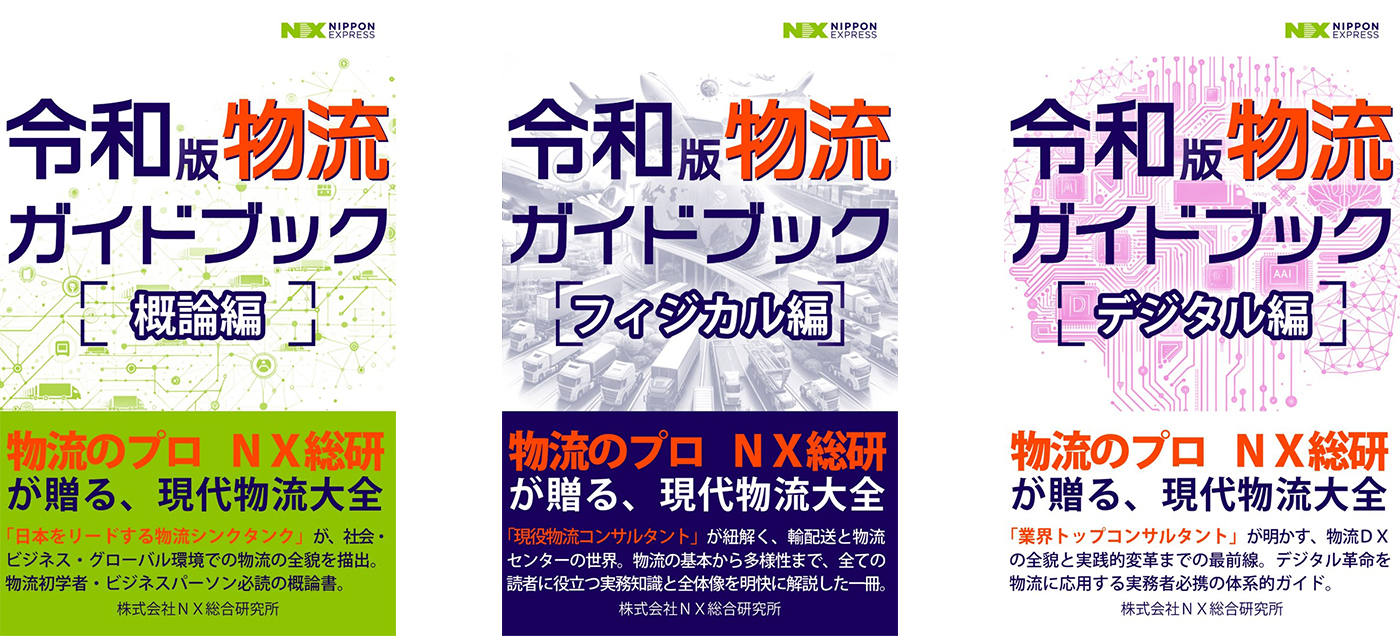
本書出版の背景
はじめに、ここ数年で物流に対する見方がどう変わってきたのかを確認してみます。昭和・平成を通して、物流はただのコストセンターだからとにかく物流コストは削減すべきだ、という考えが長年はびこってきました。それ故、いまだにそのように考える企業も残念ながらおられます。ただ、優良企業と呼ばれる「稼げる企業」は、物流に対する考え方が明らかに異なります。物流で稼ぐ、物流から価値を生み出すという考えを持っています。各種メディアでもこの認識の変化は取り上げられています。
“物流はコストセンターどころか、バリュークリエーター(価値創造の源)だ(東京大学・井村直人特任研究員)” (日経新聞電子版, 2024.5.13)
“先駆的な企業は、高度なデジタル テクノロジー、仮想化データ、コボットを使用して、サプライ チェーンのコスト センターを顧客重視の価値推進ネットワークに変革している。” (The Wall Street Journal, Aug 24, 2021)
このような報道が目立つようになったことからも、「物流がコストセンターである」という時代ではもはやないと言えるでしょう。
我々NX総合研究所は、物流が社会を支える基盤産業の一つであり、企業経営に多大な影響を及ぼすと理解しているプロフェッショナルの集団です。物流が世の中に正しく認識されること、また、物流に関わる全ての方々が正当に評価されるべきとの思いがあります。このような思いを持つ社内有志メンバーで、通常の調査・コンサルティング業務とは関係なく、今回「令和版 物流ガイドブック」プロジェクトを始動させました。
ではなぜこのような書籍を今、世の中に出す送り出すのでしょうか。これまで物流は荷主の本業とは切り離されて考えられることが多く、世間でも目立たない存在でした。しかし、コロナ禍前から懸念が始まっていたドライバー不足、コロナ禍でのサプライチェーンの混乱等から、ここ数年で真剣に物流に向き合わざるを得ない状況に直面しました。特に、コロナ禍でのEC利用の急増や店頭からモノがなくなるといった経験をし、2024年問題という言葉が毎日メディアに取り上げられていることから、一般の方が物流を意識する機会が明らかに増えました。企業にとっては、コロナ禍の海上・航空輸送運賃の高騰、在庫増加等で、これまで以上に真剣に物流に取組みましたし、2024年問題対応で物流を再考せざるを得なくなりました。このように、今はまさに物流にスポットライトが当たっているタイミングであると言えるのです。
また、物流はサプライチェーンの一部にも関わらず、かつては物流単体・単独部署で考えることが多かったと思います。しかし、物流は調達・生産・販売と密接にリンクしているという認識がこの数年で強くなっており、SCM部門担当者が物流を知るニーズが明らかに高まっている、と当社では認識しています。このような背景を踏まえ、物流専門シンクタンク、コンサルティング企業として、世の中に物流の重要性を発信することが重要だと考えました。
本書の特徴
本書は当社の多くのメンバーが各自専門分野を執筆し、編集に携わりました。物流の専門書ではありますが、教科書ではありません。そのため、多くの重要トピックはカバーしているものの、網羅性を意識していません。当社知見があるテーマについてよりリアルな内容を盛り込んでおり、それらテーマの理解のため最低限押さえて欲しい基礎情報を纏めました。また、多くの方に物流に気軽に触れてもらうため、分厚い本にせず、簡潔かつ極力短く、を心掛けました。初級者から実務者までカバーする粒度の内容が含まれますので、まんべんなく全てを読む必要はなく、興味のあるトピックに目を通していただければと思います。
概論編は、物流に関与している・していないに関わらず、全ての人に読んでもらいたい一冊です。広範囲なテーマを物流観点から切り込み解説しています。ECや災害対応、SDGs等、学生や一般の方にもなじみのあるテーマも多く、その意味で教科書的な一面があります。
フィジカル編は、3編の中で最もリアルで実務専門性が高い内容を含んでいます。物流実務経験者が執筆しており、この仕事を経験した人でないと見えない世界が満載です。本書は「輸配送」と「物流センター」の2パートで構成しています。「輸配送」は5つの輸送モード詳細を解説しています。かなり実務寄りの内容なので、難しいと感じるかもしれませんが、一般の方は普段見えない世界を垣間見ていただけますし、実務者には業務のおさらいかつ新たな観点の発見に役立つことでしょう。「物流センター」パートは、当社コンサルタントで物流センター改善や在庫削減等の実務を担当しているコンサルタントが執筆しました。実コンサル案件の知見を踏まえて、ポイントを簡潔にまとめています。一方で、物流センターに導入する設備や機器等の技術詳細までは触れていません。
デジタル編は、日々進化する物流DXをゼロから学ぶことができます。非効率さが目立つ日本の物流では、DX化が非常に注目されていまので、本書前半では物流DXが何を指しているのか、どんなツールがあるのかという基本的な内容をまずは押さえています。後半では、執筆者である現役コンサルタントの実案件の経験をもとに、実践的に活用できる知識を紹介しています。図表を活用し、内容もできる限りコンパクトにまとめました。
出版形態ですが、3編ともKindle Storeでの電子書籍としての販売ですが、ペーパーバック版を選択いただくと、A4冊子として購入者指定の住所に配送されます。
先述の通り、本書は物流トピックを完全網羅しているわけでなくトピックにより内容の深さも異なるので、読者のみなさんからは様々なご指摘を頂けるのではないかと思います。当社メンバーはそのようなコメントを歓迎します。読者の皆さんとのコミュニケーションから新たな議論が生まれ熟考することで、当社は日本の物流のさらなる発展に寄与したいと思います。最後に、本書を通じて皆さんに物流の楽しさ、奥深さを感じていただけるよう願っています。
(この記事は2024年5月15日の情報を元に執筆しました。)
(参照資料)
・The Wall Street Journal. “Supply Unchained: From Cost Center to Value Driver(Aug 24, 2021)”, (2024年5月15日参照)
・日本経済新聞電子版. “物流危機と起業家精神 ヤマト・Amazon超えの発想を(2024年5月13日)”(会員限定記事です。), (2024年5月15日参照)